明祓洞の護符・御札その8detail08
| 護符・御札コム 明祓洞トップ | > | 護符・御札一覧 | > | 08厄年関係 |
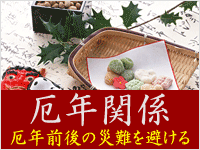
厄年の災難をさけるための護符・御札です。平安時代にはすでに記録に残っており、厄災が多く降りかかるとされる特定の年齢には、必ずこのような護符・御札を持って、災厄を遠ざけ、運を下げない行動が必要です。
明祓洞ではこれらの護符・御札を、ご注文を受けてから古式にのっとり、修行を積んだ修験者が吉日を選んで謹製しております。効験あらたかな護符・御札を、ぜひお使いくださいませ。
男性と女性の厄年は異なり、本厄は男性の場合、数え年で25歳、42歳、61歳、女性の場合は19歳、33歳、37歳とされています。特に男性の42歳、女性の33歳は大厄と呼ばれ、凶事や災難に遭う率が非常に高いので、充分な警戒を要します。
よく質問のある数え年の計算方法ですが、元日から誕生日前日午後12時までは「満年齢+2」、それ以降は「満年齢+1」で計算します。
いずれの厄年にもその前後1年間に前厄(厄の前兆が現れるとされる年)・後厄(厄のおそれが薄らいでいくとされる年)の期間があり、本厄と同様に充分に注意すべきです。
【 厄年の歴史】
厄年についての古文書には、平安時代『色葉字類抄』、鎌倉時代『拾芥抄』『仏説灌頂菩薩経』、江戸時代『和漢三才図会』などがあります。また、厄年のような考え方は日本固有のものではなく、イギリスやスペインなどのキリスト教国、エジプトやトルコなどのイスラム教国にも同じような風習があるそうです。
厄年の起源は中国の陰陽道にあります。陰陽道というのは、広辞苑第五版によれば、古代中国の陰陽五行説に基づいて天文・暦数・卜筮・卜地などをあつかう方術のことです。
平安時代に陰陽道を広めたのが、有名な安倍晴明(あべのせいめい)です。やがて陰陽道をもとに日時や方位の吉凶が定められるようになり、同時に災いを招きやすい年である厄年ができたと考えられています。
「厄年関係」の護符・御札
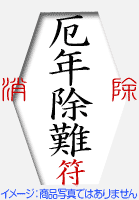
■ 厄年除難 符
商品番号 GY01T 使用法:
佩帶・
張貼・
祭拜
製作可否:
5,000円[税込]
男性と女性の厄年は異なり、本厄は男性の場合、数え年で25歳、42歳、61歳、女性の場合は19歳、33歳、37歳です。厄年には凶事や災難にあう率が非常に高いので十分な警戒を要します。この護符は厄年当年の厄を祓います。男女の別がありますので、忘れずに選んでください。いつも身に付ける佩帶法、柱や入口の上に貼る張貼法、神棚や仏壇に安置する祭拜法の、どの方法によっても効験を顕します。
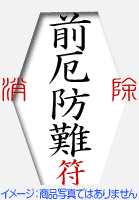
■ 前厄防難 符
商品番号 GY02T 使用法:
佩帶・
張貼・
祭拜
製作可否:
5,000円[税込]
本厄とは異なり、その前年を前厄(まえやく)と呼び、厄の前兆が現れる危険な歳であると、古来から言われています。この護符は前厄に所持して、厄除けを行うものです。男女の別があります。いつも身に付ける佩帶法、柱や入口の上に貼る張貼法、神棚や仏壇に安置する祭拜法の、どの方法によっても効験を顕します。
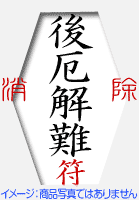
■ 後厄解難 符
商品番号 GY03T 使用法:
佩帶・
張貼・
祭拜
製作可否:
5,000円[税込]
厄年の後の歳を後厄(あとやく)と言い、厄の災いが薄れてゆくがまだ残っている歳として、十分注意をする1年間だと言われています。後厄にはこの護符を所持して、厄除けに努めましょう。男女の別があります。いつも身に付ける佩帶法、柱や入口の上に貼る張貼法、神棚や仏壇に安置する祭拜法の、どの方法によっても効験を顕します。
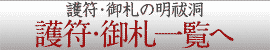
 別ジャンルの護符・御札はこちらで
別ジャンルの護符・御札はこちらで
明祓洞の護符・御札の品質表示
| サイズ | 56ミリ×33ミリ、厚さ2ミリ(種類により前後有) |
|---|---|
| 材質 | 和紙、中性紙、一部にコートフィルム(種類により異なる) |
| 重量 | 4グラム〜10グラム(種類により異なる) |
| 備考 | 護符・御札の記入は墨書、簡易印刷、朱書、朱肉を用いております。また、材質には強度・美観を増すために、コートフィルムを使用しています。護符御札を飲み込むことはおやめください。 |
| 製作者 | 明祓洞所属修験者 |
